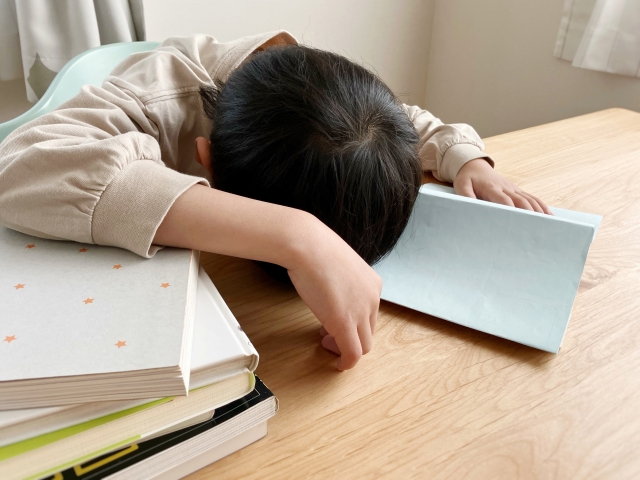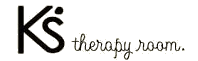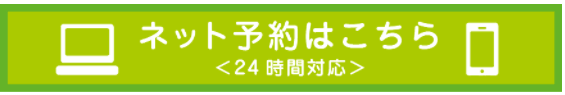心臓が激しく脈打つ・・呼吸ができない・・!
このままでは、死んでしまう‼
予告もなく動悸、脈は頻拍し。手足が痺れる。呼吸が浅くなり、過呼吸。大げさではなく“死”を意識する。
こういった症状をパニック発作と言いますが、まさしくパニック障害の中核をなす症状です。
今回は、そんな恐ろしい病、パニック障害についてダン・J・スタイン/エリック・ホランダー編成の不安障害(textbook of anxiety disorders)日本評論社から引用する形で説明していきたいと思います。

パニック障害とは
著書では、マーク・H・ポラックなど共著でパニック障害の現象学としてとりまとめています。
パニック障害では、予期せぬパニック発作が頻発した後、少なくとも1ヵ月の間予期不安(また発作が起こるのではないかという不安)を経験し、発作が起きそうな嫌な感じに襲われては心配する、ということが続く
とあります。
パニック障害の診断にはパニック発作と予期不安の症状が特徴とのことです。
また、パニック発作の症状は、情動的症状ではなく身体的症状がほとんどであることは合わせて知っておきたいところです。
またパニック障害には広場恐怖という症状があり、広場恐怖について以下のように書いてあります。
3/4以上のパニック障害患者が、少なくとも中程度の広場恐怖回避を報告している(Breier et al.1986)。広場恐怖という診断は、逃げるに逃げられない、または逃げたら恥をかくような状況や、パニック発作が起きた時に助けが得られないな状況に対する不安や回避によってつけられる
広場恐怖の対象となる状況というのはさまざまで、たとえば、1人でいること、公共の交通機関を利用すること、橋を渡ること、エレベーターやトンネル、スーパーにいること、長い列に並んでいること、以前に一度パニック発作を起こしたことがある場所や状況等があげられる
パニック障害の多くが広場恐怖を併発症として持ちます。しかし、広場恐怖を持たないパニック障害者もいることを合わせて知っておきましょう。
また、
パニック障害と診断するためには、パニック発作が、物質使用(例:乱用薬物、投薬)や、身体疾患によって誘発された生理的作用ではないことに加え、たとえば、社会不安障害や特定の恐怖症、外傷後ストレス障害、またはうつ病等の他の精神疾患と関連してみられる不安ではうまく説明されないことが条件である
とあります。
パニック障害と診断されるには、薬物の離脱症状や身体疾患ではなく、社会不安障害などのその他の精神疾患が原因ではないことが条件のようです。
ということは、その他の原因でも発作は起こるので、混同しないようにということです。

パニック障害の原因
著書では、ジェレミー・D・コプラン/ジャック・M・ゴーマン著、パニック障害の病因論としてとりまとめてあります。
少なくとも3つの中枢での神経伝達システム(中略)これらの神経伝達物質システムは、典型的な神経内分泌的ストレス反応と関係しており(中略)主たる病変は、視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸の活動亢進とclonidineに対する成長ホルモン(GH)反応の減弱によって示される
パニック障害においてすでに十分に立証されている喚気の異常と、ストレスや前述の神経生物学的システムとの関連
などとあります。
ここでも、身体的な病態システムの話に終始していて、パニック障害に関しては何がストレスでという原因はハッキリしていないようです。
パニック障害の治療
パニック障害の治療には薬物療法と心理療法があります。
ここでは、主に心理療法についてお伝えしていきます。
著書では、デビット・A・スピーゲル/ステファン・G・ホフマン著、パニック障害の心理療法としてとりまとめてあります。
近年、パニック障害と広場恐怖に対する治療法が急増し、新たに薬理学的、生理学的、認知的、行動的(中略)治療法が用いられるようになった。実際、他のどんな精神疾患よりも、パニック障害に対する有効性の確認されている治療法の数は多い
パニック障害に対して複数の治療様式を組み合わせて用いることが一般的となっている
最も頻繁に用いられる組み合わせとしては、心理社会的治療法と薬物療法の併用、およびCBTのさまざまな構成要素と広場恐怖に対するエクスポージャーの併用があげられる
とあります。
他の精神疾患と比べ、パニック障害に対する治療法は有効なものが多く出てきているようです。しかし、どの治療法を使えばいいかというより、複合的に治療をおこなうというものが最も効果的という結論のようです。
ここでは、代表的な心理療法を2つ紹介します。
・エクスポージャー
1960年代から1970年代にかけて、恐怖状況に対するイメージエクスポージャーと筋弛緩の併用による系統的脱感作法が治療の主流であった
系統的脱感作法は広場恐怖に対してほとんど効果をもたないことが数々の研究結果によって示され(Gelder and Marks 1966;Marks1971)、次第に現実エクスポージャーにとってかわられるようになった
・CBT(認知行動療法)
研究の最も進んだ治療法はパニック発作コントロール療法(Panic Control Treatment:PCT;Barlow and Craske 1994)である
PCTは不安やパニック発作に関する心理教育、不安とそれに随伴する結果に関する不適切な考えの同定と変容、深呼吸のように覚醒を低減させる技法のトレーニング、および不安とパニック発作が起こったときに生じる身体感覚への段階的エクスポージャー(内部感覚へのエクスポージャー)という要素によって構成されている
ちょっと難しいですが、現実エクスポージャーは治療者と共に発作をおこした場所に行ってみるということのようです。PCTはリラクゼーション法と認知の修正と内部感覚へのエクスポージャーを合わせておこなうという感じのようです。
治療の併用。確かに臨床でも、繰り返される自律神経の乱れ、パニック発作が連発しているという状態でのカウンセリングやエクスポージャーは非常に難しいです。
まずは、薬物療法やリラクゼーション法を使い、話ができるぐらいにはならないとカウンセリングやエクスポージャーでの治療は難しいでしょう。
まとめ
著書中にもありますが、パニック障害の人は情動的症状ではなく身体的症状がほとんどです。つまり、パニック障害や自律神経失調症などの病気を持つ方は、自身の苦しさを感情として表現するのが苦手な人が多い印象です。ストレスを身体表現化してしまっていて、何をストレスと感じていて、何が辛いのかという感情を言語化することが難しい特徴があると個人的にはとらえています。
また、広場恐怖という恐怖は、逃げるに逃げられないという恐怖を抱いているという話でしだが。公共の交通機関を利用することや、エレベーターやトンネルなどと、本来、まったく恐怖と無縁の場面で発作をおこしています。
パニック障害の人は何を恐れているのだろうか?何から逃げられなかったのだろうか?
もう少し、話を深堀っていくと、かつて逃げられない状況にいて苦しかったという経験をしている人が多くいることが分かります。
かつて、家庭環境で、学校で、あるいは特定の人間関係から逃げられなかった。
そう考えると、広場恐怖はトラウマのフラッシュバックのようにも感じます。
パニック障害の人たちはかつて逃げられない状況に苦しんできたが、感情表現が苦手で、苦しさをうまく表現してこられなかった人たちなのではないかと、そう個人的にはとらえています。
以上、あくまでも臨床経験から導き出した個人的見解ですが、あながち間違っていないとは思いますので、参考にしていただけたら幸いです。